近くにいるのに、
星のように眩しかったんだよ。
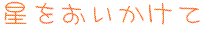 『星を見ると、なんだか不思議な気分にならない?』
そう、嬉しそうに語るタクを見た日から、
俺の中でタクは、星、だった。
「ねー、タクってばー。遊ぼうよー」
「待っててって言ってるだろ。あと少し」
「さっきからそればっかじゃん」
武蔵森男子寮の自室で、ベッドに座りながらタクを見つめる。
結構前から、ずっとこのままだ。1時間くらい。
ひまでひまで仕方がない俺をよそに、
タクは黙々と課題のプリントを仕上げる。
枕をボンッと叩いてやつあたりをしてから、
またタクに声をかけた。
「タクー」
「もう、誠二!集中できないって」
「だってー」
だって。
昨日やっと俺が告白して、
昨日やっと両思いになれて、
昨日やっと、これからは変われるんだと思ったのに。
なにも変わってない。
この枕もこのベッドもこの部屋も、目の前のタクも。
ぶーっとぶう垂れてる俺に、タクがやっと声をかけた。
「誠二は宿題終わったの?」
何かと思ったら、それか。
はぁーっとため息をつくと、タクは眉をひそめた。
終わったわけがないことくらい、分かってるだろ?
枕をぎゅっと抱きしめながら、タクの目を見上げる。
「ねぇ、タク」
「何」
ああ、本気で鬱陶しそうな声色。
俺は少しだけさみしくなって、そのまま枕に顔を伏せた。
「俺ってタクの、何?」
その質問に、タクは一瞬だけとまどってから、
俺の顔も見ずにいった。
枕から顔をあげても、交わらない目線。
「彼氏じゃないの?」
「そうだろ、親友兼」
うん、とタクは呟いた。
その視線はまだプリントに突き刺さったまま。
「俺のこと、すき?」
また、質問を投げると、
また、一瞬だけとまどってから、
また、顔も見ずにいわれた。
「すき」
冷たいなあ、とむなしくなってきた。
そんな冷たいタクだってもちろん、
全てがだいすき、なのだけれど。
いくら会話の内容に「彼氏」とか「すき」とか
いくらそんな単語が出てきたって、
やっぱり何も変わってない気がするんだから。
「だったら、どうして」
「ねえ、誠二」
遊んでくれないの?
そう聞こうと思った口は、タクに遮られた。
ああ、またきっと、君は
うるさいって、俺を怒るんだ。
「付き合うって、どういうこと?」
「…え?」
いじけて枕の糸くずを拾っていた俺が顔を上げると、
今度はしっかりと、タクの大きな眼に絡み合う視線。
「すきって言ったりキスしたり、もっと言ったらSEXしたり。それだけ?」
「…どういう、こと…?」
シャーペンをとり落としたまま、タクは、
聞いたこともないくらい寂しそうな声で、言った。
「俺を信じてない?」
その言葉に、ズキッと、
俺の心臓は痛みを感じる。
「…ごめん、ちょっと頭冷やしてくるよ」
やりかけのプリントを残したまま、
ドアの外に駆け出していってしまったタクに、
ここで追いかけなくちゃ馬鹿どころじゃない、と
自分に鞭をうって俺も走ってあとを追った。
はぁはぁ、と俺の息が荒い波をうつ。
気付けば学校の敷地外まで来てしまっていて、
ただひたすら、タクの後を追うほかに術がなかった。
「…タクっ!」
名前をよぶ、届かない。
頭上には一等星から裸眼では見えないものまで、
果てしない星が輝いてみえる。
タクの背中が、その星たちと似て見えた。
「タク!!」
もういちど、名前を呼ぶ。
さっきから何度も何度も、必死で。
もうここは、俺の知らない町並みで、
諦めて帰ろうなんて、みじんにも思わなかったけど、
億がいち、思ったとしても寮への道のりすらもう分からなかった。
自信のあるはずの体力も、大分落ちてきたところ。
俺より体力がないタクは、そろそろ…
そう思って顔をあげると、
背中を向けたまま、立ち尽くしている見慣れた姿があった。
肩が、はぁはぁと息をしている。
そのうしろ姿が、とてつもなく小さくみえて俺は、一目も気にしずに抱きついた。
あまり人通りのないこの道でも、
さっきからパラパラと人が俺たちを見つめる。
それを気にしていても、いなくても、どうでもよくて。
無言のまま、その体制のまま、何分か時は流れた。
「…誠二、」
「ん?」
声がして、タクの背中が分からないほど小さく振動する。
「わからないんだ、」
「…何が?」
「誠二のことが、すきすぎて、」
「………」
ただ静かに、いつも聴かせてくれるピアノの音色のように、
タクは話した。
遥か上にある星たちも、
俺たちの噂話をしているようだった。
「付き合ってたから成績が落ちたとか、サッカーの練習に身が入らないとか、」
「………」
「そんなこと言われたくなくて、今日いちにち、普段通りにしてたつもりだったんだけど、」
「………」
「それじゃあ、もの足りない俺もいて、」
「………」
「どうしたら、いいんだろう…」
「……タク、」
顔を向かせての、軽くあまいキス。
俺には何もいえない、何もできない、ひとことで言ったら脳なしだから。
だけど、俺といるときは笑っていてほしいと思うんだよ。
わがままだって、思うけど。
「…誠二…?」
「タクがしたいように、それでいいように、振舞ってよ。俺はついてく」
「………」
「ていうか、ついてくことくらいしか、出来ないからさ」
本当に、星みたいだよ、竹巳は。
いくら夢みたって、掴んで自分のものにするなんて、絶対にできないんだ。
だけど、アポロが月に到着したときみたいに、
近づいて距離を縮めることなら、いくらでも出来るんだ。
「…ありがとう、」
「どうしたしましてっ!」
にへっと笑って、手を差し伸べる。
無力でなにもできないけど、
そばに居ることくらいはできる証として。
その手をそっと握り返してくれたタクに、
俺はただひとことを言った。
「俺らの部屋に、帰ろっか」
道ゆく人々に別れをつげて。
ねえ、近くて遠くて、
温かく輝く君と。
『星を見ると、なんだか不思議な気分にならない?』
そう、嬉しそうに語るタクを見た日から、
俺の中でタクは、星、だった。
「ねー、タクってばー。遊ぼうよー」
「待っててって言ってるだろ。あと少し」
「さっきからそればっかじゃん」
武蔵森男子寮の自室で、ベッドに座りながらタクを見つめる。
結構前から、ずっとこのままだ。1時間くらい。
ひまでひまで仕方がない俺をよそに、
タクは黙々と課題のプリントを仕上げる。
枕をボンッと叩いてやつあたりをしてから、
またタクに声をかけた。
「タクー」
「もう、誠二!集中できないって」
「だってー」
だって。
昨日やっと俺が告白して、
昨日やっと両思いになれて、
昨日やっと、これからは変われるんだと思ったのに。
なにも変わってない。
この枕もこのベッドもこの部屋も、目の前のタクも。
ぶーっとぶう垂れてる俺に、タクがやっと声をかけた。
「誠二は宿題終わったの?」
何かと思ったら、それか。
はぁーっとため息をつくと、タクは眉をひそめた。
終わったわけがないことくらい、分かってるだろ?
枕をぎゅっと抱きしめながら、タクの目を見上げる。
「ねぇ、タク」
「何」
ああ、本気で鬱陶しそうな声色。
俺は少しだけさみしくなって、そのまま枕に顔を伏せた。
「俺ってタクの、何?」
その質問に、タクは一瞬だけとまどってから、
俺の顔も見ずにいった。
枕から顔をあげても、交わらない目線。
「彼氏じゃないの?」
「そうだろ、親友兼」
うん、とタクは呟いた。
その視線はまだプリントに突き刺さったまま。
「俺のこと、すき?」
また、質問を投げると、
また、一瞬だけとまどってから、
また、顔も見ずにいわれた。
「すき」
冷たいなあ、とむなしくなってきた。
そんな冷たいタクだってもちろん、
全てがだいすき、なのだけれど。
いくら会話の内容に「彼氏」とか「すき」とか
いくらそんな単語が出てきたって、
やっぱり何も変わってない気がするんだから。
「だったら、どうして」
「ねえ、誠二」
遊んでくれないの?
そう聞こうと思った口は、タクに遮られた。
ああ、またきっと、君は
うるさいって、俺を怒るんだ。
「付き合うって、どういうこと?」
「…え?」
いじけて枕の糸くずを拾っていた俺が顔を上げると、
今度はしっかりと、タクの大きな眼に絡み合う視線。
「すきって言ったりキスしたり、もっと言ったらSEXしたり。それだけ?」
「…どういう、こと…?」
シャーペンをとり落としたまま、タクは、
聞いたこともないくらい寂しそうな声で、言った。
「俺を信じてない?」
その言葉に、ズキッと、
俺の心臓は痛みを感じる。
「…ごめん、ちょっと頭冷やしてくるよ」
やりかけのプリントを残したまま、
ドアの外に駆け出していってしまったタクに、
ここで追いかけなくちゃ馬鹿どころじゃない、と
自分に鞭をうって俺も走ってあとを追った。
はぁはぁ、と俺の息が荒い波をうつ。
気付けば学校の敷地外まで来てしまっていて、
ただひたすら、タクの後を追うほかに術がなかった。
「…タクっ!」
名前をよぶ、届かない。
頭上には一等星から裸眼では見えないものまで、
果てしない星が輝いてみえる。
タクの背中が、その星たちと似て見えた。
「タク!!」
もういちど、名前を呼ぶ。
さっきから何度も何度も、必死で。
もうここは、俺の知らない町並みで、
諦めて帰ろうなんて、みじんにも思わなかったけど、
億がいち、思ったとしても寮への道のりすらもう分からなかった。
自信のあるはずの体力も、大分落ちてきたところ。
俺より体力がないタクは、そろそろ…
そう思って顔をあげると、
背中を向けたまま、立ち尽くしている見慣れた姿があった。
肩が、はぁはぁと息をしている。
そのうしろ姿が、とてつもなく小さくみえて俺は、一目も気にしずに抱きついた。
あまり人通りのないこの道でも、
さっきからパラパラと人が俺たちを見つめる。
それを気にしていても、いなくても、どうでもよくて。
無言のまま、その体制のまま、何分か時は流れた。
「…誠二、」
「ん?」
声がして、タクの背中が分からないほど小さく振動する。
「わからないんだ、」
「…何が?」
「誠二のことが、すきすぎて、」
「………」
ただ静かに、いつも聴かせてくれるピアノの音色のように、
タクは話した。
遥か上にある星たちも、
俺たちの噂話をしているようだった。
「付き合ってたから成績が落ちたとか、サッカーの練習に身が入らないとか、」
「………」
「そんなこと言われたくなくて、今日いちにち、普段通りにしてたつもりだったんだけど、」
「………」
「それじゃあ、もの足りない俺もいて、」
「………」
「どうしたら、いいんだろう…」
「……タク、」
顔を向かせての、軽くあまいキス。
俺には何もいえない、何もできない、ひとことで言ったら脳なしだから。
だけど、俺といるときは笑っていてほしいと思うんだよ。
わがままだって、思うけど。
「…誠二…?」
「タクがしたいように、それでいいように、振舞ってよ。俺はついてく」
「………」
「ていうか、ついてくことくらいしか、出来ないからさ」
本当に、星みたいだよ、竹巳は。
いくら夢みたって、掴んで自分のものにするなんて、絶対にできないんだ。
だけど、アポロが月に到着したときみたいに、
近づいて距離を縮めることなら、いくらでも出来るんだ。
「…ありがとう、」
「どうしたしましてっ!」
にへっと笑って、手を差し伸べる。
無力でなにもできないけど、
そばに居ることくらいはできる証として。
その手をそっと握り返してくれたタクに、
俺はただひとことを言った。
「俺らの部屋に、帰ろっか」
道ゆく人々に別れをつげて。
ねえ、近くて遠くて、
温かく輝く君と。
 こわくて読み返せない…
じゃあアップすんなよ!って、ごめんなさい。
やっぱりあらすじと全然違う。
ぐは…orz
(c)愛渚 雛古 2005.09.07
こわくて読み返せない…
じゃあアップすんなよ!って、ごめんなさい。
やっぱりあらすじと全然違う。
ぐは…orz
(c)愛渚 雛古 2005.09.07
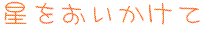 『星を見ると、なんだか不思議な気分にならない?』
そう、嬉しそうに語るタクを見た日から、
俺の中でタクは、星、だった。
「ねー、タクってばー。遊ぼうよー」
「待っててって言ってるだろ。あと少し」
「さっきからそればっかじゃん」
武蔵森男子寮の自室で、ベッドに座りながらタクを見つめる。
結構前から、ずっとこのままだ。1時間くらい。
ひまでひまで仕方がない俺をよそに、
タクは黙々と課題のプリントを仕上げる。
枕をボンッと叩いてやつあたりをしてから、
またタクに声をかけた。
「タクー」
「もう、誠二!集中できないって」
「だってー」
だって。
昨日やっと俺が告白して、
昨日やっと両思いになれて、
昨日やっと、これからは変われるんだと思ったのに。
なにも変わってない。
この枕もこのベッドもこの部屋も、目の前のタクも。
ぶーっとぶう垂れてる俺に、タクがやっと声をかけた。
「誠二は宿題終わったの?」
何かと思ったら、それか。
はぁーっとため息をつくと、タクは眉をひそめた。
終わったわけがないことくらい、分かってるだろ?
枕をぎゅっと抱きしめながら、タクの目を見上げる。
「ねぇ、タク」
「何」
ああ、本気で鬱陶しそうな声色。
俺は少しだけさみしくなって、そのまま枕に顔を伏せた。
「俺ってタクの、何?」
その質問に、タクは一瞬だけとまどってから、
俺の顔も見ずにいった。
枕から顔をあげても、交わらない目線。
「彼氏じゃないの?」
「そうだろ、親友兼」
うん、とタクは呟いた。
その視線はまだプリントに突き刺さったまま。
「俺のこと、すき?」
また、質問を投げると、
また、一瞬だけとまどってから、
また、顔も見ずにいわれた。
「すき」
冷たいなあ、とむなしくなってきた。
そんな冷たいタクだってもちろん、
全てがだいすき、なのだけれど。
いくら会話の内容に「彼氏」とか「すき」とか
いくらそんな単語が出てきたって、
やっぱり何も変わってない気がするんだから。
「だったら、どうして」
「ねえ、誠二」
遊んでくれないの?
そう聞こうと思った口は、タクに遮られた。
ああ、またきっと、君は
うるさいって、俺を怒るんだ。
「付き合うって、どういうこと?」
「…え?」
いじけて枕の糸くずを拾っていた俺が顔を上げると、
今度はしっかりと、タクの大きな眼に絡み合う視線。
「すきって言ったりキスしたり、もっと言ったらSEXしたり。それだけ?」
「…どういう、こと…?」
シャーペンをとり落としたまま、タクは、
聞いたこともないくらい寂しそうな声で、言った。
「俺を信じてない?」
その言葉に、ズキッと、
俺の心臓は痛みを感じる。
「…ごめん、ちょっと頭冷やしてくるよ」
やりかけのプリントを残したまま、
ドアの外に駆け出していってしまったタクに、
ここで追いかけなくちゃ馬鹿どころじゃない、と
自分に鞭をうって俺も走ってあとを追った。
はぁはぁ、と俺の息が荒い波をうつ。
気付けば学校の敷地外まで来てしまっていて、
ただひたすら、タクの後を追うほかに術がなかった。
「…タクっ!」
名前をよぶ、届かない。
頭上には一等星から裸眼では見えないものまで、
果てしない星が輝いてみえる。
タクの背中が、その星たちと似て見えた。
「タク!!」
もういちど、名前を呼ぶ。
さっきから何度も何度も、必死で。
もうここは、俺の知らない町並みで、
諦めて帰ろうなんて、みじんにも思わなかったけど、
億がいち、思ったとしても寮への道のりすらもう分からなかった。
自信のあるはずの体力も、大分落ちてきたところ。
俺より体力がないタクは、そろそろ…
そう思って顔をあげると、
背中を向けたまま、立ち尽くしている見慣れた姿があった。
肩が、はぁはぁと息をしている。
そのうしろ姿が、とてつもなく小さくみえて俺は、一目も気にしずに抱きついた。
あまり人通りのないこの道でも、
さっきからパラパラと人が俺たちを見つめる。
それを気にしていても、いなくても、どうでもよくて。
無言のまま、その体制のまま、何分か時は流れた。
「…誠二、」
「ん?」
声がして、タクの背中が分からないほど小さく振動する。
「わからないんだ、」
「…何が?」
「誠二のことが、すきすぎて、」
「………」
ただ静かに、いつも聴かせてくれるピアノの音色のように、
タクは話した。
遥か上にある星たちも、
俺たちの噂話をしているようだった。
「付き合ってたから成績が落ちたとか、サッカーの練習に身が入らないとか、」
「………」
「そんなこと言われたくなくて、今日いちにち、普段通りにしてたつもりだったんだけど、」
「………」
「それじゃあ、もの足りない俺もいて、」
「………」
「どうしたら、いいんだろう…」
「……タク、」
顔を向かせての、軽くあまいキス。
俺には何もいえない、何もできない、ひとことで言ったら脳なしだから。
だけど、俺といるときは笑っていてほしいと思うんだよ。
わがままだって、思うけど。
「…誠二…?」
「タクがしたいように、それでいいように、振舞ってよ。俺はついてく」
「………」
「ていうか、ついてくことくらいしか、出来ないからさ」
本当に、星みたいだよ、竹巳は。
いくら夢みたって、掴んで自分のものにするなんて、絶対にできないんだ。
だけど、アポロが月に到着したときみたいに、
近づいて距離を縮めることなら、いくらでも出来るんだ。
「…ありがとう、」
「どうしたしましてっ!」
にへっと笑って、手を差し伸べる。
無力でなにもできないけど、
そばに居ることくらいはできる証として。
その手をそっと握り返してくれたタクに、
俺はただひとことを言った。
「俺らの部屋に、帰ろっか」
道ゆく人々に別れをつげて。
ねえ、近くて遠くて、
温かく輝く君と。
『星を見ると、なんだか不思議な気分にならない?』
そう、嬉しそうに語るタクを見た日から、
俺の中でタクは、星、だった。
「ねー、タクってばー。遊ぼうよー」
「待っててって言ってるだろ。あと少し」
「さっきからそればっかじゃん」
武蔵森男子寮の自室で、ベッドに座りながらタクを見つめる。
結構前から、ずっとこのままだ。1時間くらい。
ひまでひまで仕方がない俺をよそに、
タクは黙々と課題のプリントを仕上げる。
枕をボンッと叩いてやつあたりをしてから、
またタクに声をかけた。
「タクー」
「もう、誠二!集中できないって」
「だってー」
だって。
昨日やっと俺が告白して、
昨日やっと両思いになれて、
昨日やっと、これからは変われるんだと思ったのに。
なにも変わってない。
この枕もこのベッドもこの部屋も、目の前のタクも。
ぶーっとぶう垂れてる俺に、タクがやっと声をかけた。
「誠二は宿題終わったの?」
何かと思ったら、それか。
はぁーっとため息をつくと、タクは眉をひそめた。
終わったわけがないことくらい、分かってるだろ?
枕をぎゅっと抱きしめながら、タクの目を見上げる。
「ねぇ、タク」
「何」
ああ、本気で鬱陶しそうな声色。
俺は少しだけさみしくなって、そのまま枕に顔を伏せた。
「俺ってタクの、何?」
その質問に、タクは一瞬だけとまどってから、
俺の顔も見ずにいった。
枕から顔をあげても、交わらない目線。
「彼氏じゃないの?」
「そうだろ、親友兼」
うん、とタクは呟いた。
その視線はまだプリントに突き刺さったまま。
「俺のこと、すき?」
また、質問を投げると、
また、一瞬だけとまどってから、
また、顔も見ずにいわれた。
「すき」
冷たいなあ、とむなしくなってきた。
そんな冷たいタクだってもちろん、
全てがだいすき、なのだけれど。
いくら会話の内容に「彼氏」とか「すき」とか
いくらそんな単語が出てきたって、
やっぱり何も変わってない気がするんだから。
「だったら、どうして」
「ねえ、誠二」
遊んでくれないの?
そう聞こうと思った口は、タクに遮られた。
ああ、またきっと、君は
うるさいって、俺を怒るんだ。
「付き合うって、どういうこと?」
「…え?」
いじけて枕の糸くずを拾っていた俺が顔を上げると、
今度はしっかりと、タクの大きな眼に絡み合う視線。
「すきって言ったりキスしたり、もっと言ったらSEXしたり。それだけ?」
「…どういう、こと…?」
シャーペンをとり落としたまま、タクは、
聞いたこともないくらい寂しそうな声で、言った。
「俺を信じてない?」
その言葉に、ズキッと、
俺の心臓は痛みを感じる。
「…ごめん、ちょっと頭冷やしてくるよ」
やりかけのプリントを残したまま、
ドアの外に駆け出していってしまったタクに、
ここで追いかけなくちゃ馬鹿どころじゃない、と
自分に鞭をうって俺も走ってあとを追った。
はぁはぁ、と俺の息が荒い波をうつ。
気付けば学校の敷地外まで来てしまっていて、
ただひたすら、タクの後を追うほかに術がなかった。
「…タクっ!」
名前をよぶ、届かない。
頭上には一等星から裸眼では見えないものまで、
果てしない星が輝いてみえる。
タクの背中が、その星たちと似て見えた。
「タク!!」
もういちど、名前を呼ぶ。
さっきから何度も何度も、必死で。
もうここは、俺の知らない町並みで、
諦めて帰ろうなんて、みじんにも思わなかったけど、
億がいち、思ったとしても寮への道のりすらもう分からなかった。
自信のあるはずの体力も、大分落ちてきたところ。
俺より体力がないタクは、そろそろ…
そう思って顔をあげると、
背中を向けたまま、立ち尽くしている見慣れた姿があった。
肩が、はぁはぁと息をしている。
そのうしろ姿が、とてつもなく小さくみえて俺は、一目も気にしずに抱きついた。
あまり人通りのないこの道でも、
さっきからパラパラと人が俺たちを見つめる。
それを気にしていても、いなくても、どうでもよくて。
無言のまま、その体制のまま、何分か時は流れた。
「…誠二、」
「ん?」
声がして、タクの背中が分からないほど小さく振動する。
「わからないんだ、」
「…何が?」
「誠二のことが、すきすぎて、」
「………」
ただ静かに、いつも聴かせてくれるピアノの音色のように、
タクは話した。
遥か上にある星たちも、
俺たちの噂話をしているようだった。
「付き合ってたから成績が落ちたとか、サッカーの練習に身が入らないとか、」
「………」
「そんなこと言われたくなくて、今日いちにち、普段通りにしてたつもりだったんだけど、」
「………」
「それじゃあ、もの足りない俺もいて、」
「………」
「どうしたら、いいんだろう…」
「……タク、」
顔を向かせての、軽くあまいキス。
俺には何もいえない、何もできない、ひとことで言ったら脳なしだから。
だけど、俺といるときは笑っていてほしいと思うんだよ。
わがままだって、思うけど。
「…誠二…?」
「タクがしたいように、それでいいように、振舞ってよ。俺はついてく」
「………」
「ていうか、ついてくことくらいしか、出来ないからさ」
本当に、星みたいだよ、竹巳は。
いくら夢みたって、掴んで自分のものにするなんて、絶対にできないんだ。
だけど、アポロが月に到着したときみたいに、
近づいて距離を縮めることなら、いくらでも出来るんだ。
「…ありがとう、」
「どうしたしましてっ!」
にへっと笑って、手を差し伸べる。
無力でなにもできないけど、
そばに居ることくらいはできる証として。
その手をそっと握り返してくれたタクに、
俺はただひとことを言った。
「俺らの部屋に、帰ろっか」
道ゆく人々に別れをつげて。
ねえ、近くて遠くて、
温かく輝く君と。
 こわくて読み返せない…
じゃあアップすんなよ!って、ごめんなさい。
やっぱりあらすじと全然違う。
ぐは…orz
(c)愛渚 雛古 2005.09.07
こわくて読み返せない…
じゃあアップすんなよ!って、ごめんなさい。
やっぱりあらすじと全然違う。
ぐは…orz
(c)愛渚 雛古 2005.09.07